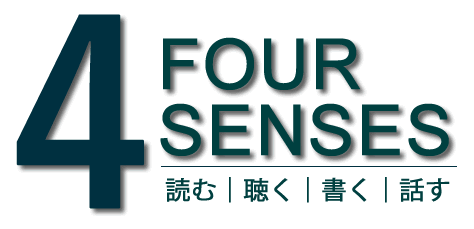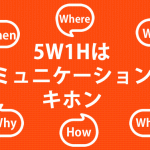AIの登場によって、私たちのコミュニケーションはもっと楽になった。いや、なるはずだった。
文章作成はわずか数分でできるし、翻訳の精度は飛躍的に向上した。しかし、ビジネスの現場でコミュニケーションの問題が一向に減らないのはなぜだろうか。正直なところ「言った/言わない」「文章が理解できない」「言葉遣いがおかしい」など、むしろ、問題はより複雑化しているようにさえ感じられる。
恐らくその根源にあるのは、私たち人間なら誰しも持っている「思い込み」だ。今回は、その「思い込み」がいかにしてコミュニケーションを崩壊させるのか、そしていったいどうすればその罠から抜け出せるのかについて、深く掘り下げていきたい。
コンテンツ
コミュニケーションのすれ違いを生む、あなたの「正しさ」
あなたは本当に、毎回必ず正しいのか?
いきなり挑発的な問いを投げかけてしまったが、少し胸に手を当てて考えてみてほしい。例えば、
- 部下からの報告が要領を得ないと感じたとき
- 「なぜ、こんな簡単なことが伝わらないんだ」と苛立ったとき
- 同僚のメールの意図が読めず、一方的に「失礼なやつだ」と断定してしまったとき
こんなシーンは毎日のようにあるが、その判断は、本当に100%正しかったと言えるのだろうか。
私たちは、自分が見えている景色や世界が「すべて」であり「正しい」と無意識に思い込んでいるというのは有名な話だ。これまで培ってきた自分の経験則や価値観というフィルターを通して、相手の言動を勝手に解釈し、評価しているとも言える。
特に、デジタル普及が進み、リモートワークが当たり前になり、テキストコミュニケーションのやり取りが爆発的に増えた現代では、この「思い込み」が暴走しやすい環境にあると言える。対面であれば表情や声のトーンで補完されるはずの「ノンバーバルな情報」が、テキストではごっそりと抜け落ちていく。
AIがどれだけ文章が上手になったとしても、文意が正しく伝わらず解釈されていなかったり、また結局何が言いたいのか分からないものも相変わらず発生する。結果、読み手がそれを受け取った時にはすでに欠落した情報を自らの「想像や経験」で補うしかなくなり、そこに深刻なすれ違いが生まれる。例えば以下の一文を送る/受け取るとしよう。
「この前依頼した件、どうなってる?」
もしこの一文だけ送られてきたら、受け手側はどう感じるだろうか。「単純な進捗確認だろう」と捉える人も多いだろうが、もしかしたら「急かされている」「責められている」と感じる人もいるかもしれない。(実際、マルハラのような言葉も出てきている)
送り手には何の悪気もなくても、受け手の状況や心の状態、そして送り手に対する「決めつけ」によって、その意味は180度変わってしまう。これほど恐ろしいことは無い。
であるからこそ、文章で伝えきれないのであれば電話やオンライン、オフラインの打ち合わせをすべきだが、それも実施しない。多忙を理由にそれすら怠り、「言わなくても分かるだろう」「このくらい読み取って当然だ」と、読み手(受け手)の読解力に依存するようなコミュニケーションの取り方をするのは最悪だ。それは、コミュニケーションとは名ばかりの、ただの「情報の押し付け」でしかない。
勝手な想像や決めつけ(レッテル貼り)をやめる
では、どうすればこの「思い込み」の罠から抜け出せるのか。答えは驚くほどシンプルだ。
「だから背景を聞くというコミュニケーションを徹底する」ことだ。
相手の言葉尻を捉えて反射的に反応するのではなく、一度立ち止まってみる。「なぜ、彼はこう言っているのだろう?」「彼女がこの言葉を選んだ背景には、何があるのだろう?」と、相手の立場に立って想像力を働かせることが大切だ。
例えば、部下が「新商品のターゲットは20代女性がいいと思います」と提案してきたとする。多くの管理職は「いや、それは市場が小さすぎる」と即座に反応してしまいがちだ。
しかし、まずは背景を聞いてみてほしい。
「なるほど、20代女性をターゲットにしようと思ったのはどんな理由からですか?」
「どんなデータや体験があなたのその判断につながったのでしょうか?」
すると、実は「競合他社が手薄なセグメントで、SNSでの拡散力が期待できる」「最近の展示会で20代女性からの反応が特に良かった」といった具体的な根拠が出てくるかもしれない。
これはきちんとその背景を訪ねる事でしか得られない情報であり、思い込みから断定しままったら(部下の意図を)絶対に手に入れることができない。
- 「要領を得ない報告」をしてくる部下は、もしかしたら複数の部署から矛盾した指示を受けて混乱しているのかもしれない
- 「意図が不明なメール」を送ってきた同僚は、緊急のトラブル対応に追われ、詳細を書く時間すらなかったのかもしれない
そんな風に想像することができるかどうかだ。こちらの勝手な想像や決めつけ(レッテル貼り)をしてコミュニケーションを進めてはならない。
もちろんこれは「言うは易く行うは難し」だ。ビジネスには納期があり、予算がある。他にもやらなければならないことは山ほどある。いちいちすべての背景など検討していられないというのも事実だろう。しかし、思い込みを排除する努力は継続しなければ治るものでもない。最初は時間がかかってしまうが、長期的に見れば効率の良いコミュニケーションであるはずだ。
自分の正しさではなくビジネスの目的に沿って判断する
私たちは常に「自分の正しさ」を証明したい生き物だ。しかし、その小さなプライドを守るために、決めつけたコミュニケーションを取ってはいけない。これは、発信側も受信側も同じことが言える。「こうに違いない」からスタートしてしまうと、「そことマッチしているかどうか」だけで判断してしまう。
相手の言っていることが分からないなら質問すればいい。「すみません、〇〇の件ですが、もう少し背景を教えていただけますか?」「認識の齟齬を防ぎたいので、この部分の意図を確認させてください」といったコミュニケーションをとる。たったこれだけで、お互いの不要な憶測や誤解のほとんどは防げるようになる。
無意識の「マウント」がハラスメントになる瞬間
「思い込み」がさらに危険な形で表出するのが、ハラスメントととられるようなマウントコミュニケーションだ。これは、自分の優位性を示したいという無意識の欲求が、いつのまにか相手を貶める言動として現れる現象でもある。
例えば、こんな会話はないだろうか。
部下: 「〇〇社の件、先方の担当者にご連絡したのですが、まだお返事がいただけておりません。」
上司: 「え、まだ返事ないの? 普通、24時間以内には返すのがビジネスマナーでしょ。どんな聞き方したの? そもそも、君の頼み方が悪いんじゃないの?」
この上司の場合、部下が直面している状況の背景を聞こうとせず、「返事がない=部下の能力が低い」と決めつけている。最後の「そもそも~」という一言は、完全に部下の人格を否定するマウントだ。良かれと思って指導しているつもりかもしれないが、これは部下のやる気を削ぎ、心理的安全性を破壊してしまう可能性が高い。
さらに、こんなパターンもある。
同僚A: 「このプロジェクトの件、私はA案が良いと思います。理由は…」
同僚B: 「(話を遮って)要するに、コストをかけたくないってことでしょ? でも、それだとクオリティが担保できないよね。はい、論破。」
これも相手の意見を最後まで聞かず、自分の解釈という枠に無理やり押し込め、「要するに」という言葉で片付けてしまう。「要するに」というのはその一連の話をまとめるということだが、話を全部聞いていない状態での「要するに」は、ただの決めつけでしかないのは明白だ。
こういったやり取りも悪質なマウントコミュニケーションだ。相手の思考を尊重せず、自分の土俵に引きずり込んでねじ伏せるような行為は、前向きで健全な議論を阻害し、チームの創造性を奪う可能性すらある。発言すること自体が恐怖になる。
こうしたコミュニケーションが多くなるといずれ誰も本音で話さなくなり、イノベーションは停滞し、優秀な人材から去っていく。現代のハラスメント防止の観点からも、こうしたマウントコミュニケーションは非常にリスクが高い行為で即刻中止すべきだろう。
「相手視点」と「自分視点」の使い分けこそが要諦
ここまで、「思い込み」の危険性と、背景を聞くことの重要性を説明してきたがこれを実践するための核となる考え方が、コミュニケーションの要諦は「相手の立場」での視点と「自分の立場」での視点の使い分けである という発想だ。
- 「相手の立場」での視点を持つための傾聴: 相手の発言の背景には何があるのか? 相手は何を懸念し、何を期待しているのか?何を意図しているのか? まずは自分の評価や判断を保留し、相手の世界を理解しようと努めるフェーズ。
- 「自分の立場」での視点からの主張: 相手の背景を理解した上で、自分の意見や要望、事実を明確に伝えるフェーズ。ここでは、曖昧な表現を避け、論理的かつ具体的に話すことが求められる。
このように、多くのコミュニケーション不全は、この二つの視点のどちらかが欠けているか、あるいは使う順番を間違えているために起きているのではないだろうか。
自分の主張ばかりで相手の話を聞かない「自分視点オンリー」の場合も、相手に気を遣うあまり、自分の意見を言えない「相手視点オンリー」場合のどちらも、本質的な相互理解には至らない。
まずは「相手視点」で徹底的に聞き、相手の背景を理解する。そして、その上で「自分視点」で誠実に、かつ明確に伝える。この順番を間違えてはいけない。
特にテキストコミュニケーションでは、相手が迷わないよう具体的で明確な表現を心がけたい。
×「例のあの件、よろしくお願いします」
○「昨日お話しした新商品のパッケージデザインの件、明日の15時までに初稿をお送りいただけますでしょうか」
×「至急対応をお願いします」
○ 「A社からのクレーム対応の件、明日の朝一で部長への報告が必要なため、今日の18時までに状況をまとめていただけますでしょうか」
このキャッチボールができて初めて、コミュニケーションは「作業」から「協働」「共創」フェーズへと進化する。
組織のコミュニケーション改善のための具体的施策とは
組織のコミュニケーション改善のためにできることは意外と多い。
- 研修プログラムの見直し:従来のビジネスマナー研修に加えて、「相手の立場で考える」「背景を聞く質問力」「具体的な伝え方」にフォーカスした実践的なコミュニケーション研修の導入
- 1on1ミーティングの質向上 定期的な1on1:「最近、誤解やすれ違いはありませんか?」「チーム内のコミュニケーションで気になることはありますか?」といった質問を加えることで、コミュニケーション上での問題の早期発見につながる
- テキストコミュニケーションのガイドラインの策定 :メールやチャットでのやり取りにおける最低限のルール(件名の付け方、必要な情報の明記、DM は使用不可など)を策定し、全社で共有する
結論:コミュニケーションとは、組織の未来を創る投資である
冒頭にも述べたように AIは確かに優秀なアシスタントだが、コミュニケーションの主体は、あくまで私たち人間だし、これからもそうでなくてはならない。AIがどれだけ進化しても、相手の心の機微を察し、その背景に寄り添うことはできない。
あなたの組織では、思い込みや決めつけが横行していないだろうか。無用なマウントで、メンバーの創造性や才能の芽を摘んでいないだろうか。
実はコミュニケーションコストは、目に見えず、定量化しにくい。コミュニケーションを取っている同士が一番感じていることだが、それを数値で報告することはかなり難しいからだ。しかし、放置すれば確実に組織を蝕んでいく。テキストでのコミュニケーションや絵文字文化による文章の省略、動画によるコミュニケーションが全盛の時代だからこそ、私たち一人ひとりが自らの「思い込み」と向き合い、相手の背景にじっと耳を澄ます勇気を持つべきだ。
繰り返すが、AIがどれだけ発達しても、思い込みを解消し、相手の立場で考え、背景を聞き、具体的に伝えるというコミュニケーションの本質は、私たち人間にしかできないことだ。その地道な一歩こそが、不毛なすれ違いをなくし、強靭でしなやかな組織文化を育む、最も確実な投資である。

トライベクトル株式会社 代表取締役。会社経営 19年目。翻訳・ローカライズ業界24年。翻訳・ローカライズ実績年間10,000件以上。
現在は BtoB (特に IT 企業)専門のマーケティングサポート(動画や導入事例などのコンテンツ制作全般)と言語サービス(翻訳、オンライン通訳、英会話、e-learning 講座等)を行っています。